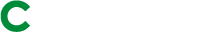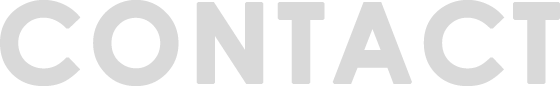福岡で事業を始める・拡大するなら
個人事業主と法人成り(法人化)どちらを選ぶ?判断基準とタイミングを実務経験から解説。
福岡で事業を始める方、すでに個人事業主として活動されている方へ。「このまま個人事業主でいくか、法人成りすべきか」は多くの経営者が悩むポイントです。福岡で数多くの起業・法人成り支援を行ってきた中小企業診断士が、実務的な判断基準とベストタイミングを分かりやすく解説します。
- ✔ 個人事業主:開業手続きが簡単・維持費用が安い・経営の自由度高い ∕ 社会的信用・税負担・資金調達に限界
- ✔ 法人:社会的信用度・節税効果・資金調達力が向上 ∕ 設立手続き・維持コストが増加
- ✔ 判断基準:個人により異なるが、年間所得金額 800 万円程度が一つの目安。従業員雇用や大企業との取引も重要な判断要素
- ✔ ベストタイミング:一律のベストタイミングはない。それぞれの事情に応じて、さまざまな要素を検討したうえで判断が必要。
そもそも何が違う?個人事業主と法人の基本
個人事業主とは
「あなた個人の名前」で事業を行う方法です。まるで「○○商店」みたいなイメージです。たとえば「武蔵太陽」さんがパン屋さんを始めたら「武蔵ベーカリー」という感じ。あなた自身が看板になって、あなたの名前で事業を開始します。
始めるのはとっても簡単!税務署に「開業届」という書類を 1 枚提出するだけで、今日からでもお店や事業を始められます。法人登記も不要で、手数料もかかりません。
法人とは
「会社」という新しい法人格を作って、その会社名で事業を行う方法です。少し不思議ですが、法律の世界では「会社」も一人の人間のように扱われます。だから「武蔵太陽」さんが「株式会社MUSASHI」を設立したら、武蔵さんは会社の「代表者」(社長)という立場になります。
始めるには法務局という役所で「法人登記」という手続きが必要で、個人事業主より手間と登録免許税などの費用がかかります。また、定款という会社のルールブックの作成も義務付けられています。
【実務判断フローチャート】あなたはどちら向き?
ステップ 1:売上・所得で判断
年間売上 1,000 万円超 → 法人化を検討(消費税の影響大)。
年間所得 800 万円程度 → 法人化のメリットが出やすい※。
年間所得 500 万円未満 → 個人事業主のまま様子見が一般的。
※ただし、維持費・税理士費用・社会保険料負担等を総合的に考慮する必要があり、個人の状況により大きく異なります。
ステップ 2:事業内容・取引先で判断
BtoB メイン・大手企業取引希望 → 法人化推奨。
店舗型サービス・地域密着型 → 個人事業主でも可。
IT・コンサル・専門サービス → 法人化で信用力 UP。
ステップ 3:将来計画で判断
従業員を雇う予定 → 法人化推奨。
事業拡大・投資予定 → 法人化で資金調達有利。
現状維持・一人で続ける → 個人事業主で OK。
個人事業主の良いところ・困るところ
良いところ(メリット)
- 開業手続きが非常に簡単
- 開業届という書類 1 枚を税務署に提出するだけ。手数料もかからないし、今日から「経営者」になれちゃいます!
- 維持費用がほとんどかからない
- 年間の固定費はほぼゼロ。確定申告も、法人と比較したらずっと簡単です。
- 経営の自由度が高い
- 売上の管理も経費計上も、全部自分のペースで OK。煩雑な事務作業も最小限です。
- 赤字でも固定の税負担がない
- もし利益が出ない年があっても、法人のように毎年決まった法人住民税を納付する義務がありません。
困るところ(デメリット)
- 社会的信用に限界がある
- 基本的には、事業実績等が社会的信用につながりますが、「田中商店」より「株式会社田中」の方が、取引先や金融機関から信頼されやすい面があるのも現実です。
- 所得が増加すると税負担が重くなる
- 個人の所得税は累進課税で、所得額が増えるほど税率が上がります。最高で約 55% も!法人税(約 30%)の方が安くなるケースがあります。
- 資金調達の選択肢が限定される
- 銀行融資は可能ですが、投資家からの出資を受けたり、株式を発行したりは基本的にできません。
- 従業員雇用時の制約が大きい
- 労働保険や社会保険の手続きが複雑です。優秀な人材の採用も、法人の方が有利な傾向があります。
法人の良いところ・困るところ
良いところ(メリット)
- 社会的信用度が格段に向上
- 福岡の大企業との取引では、法人格が条件になるケースもあります。
- 節税効果が大きくなる可能性
-
- 所得が一定水準になると、法人税の方が税負担が軽くなります。
- 役員報酬として給与を受け取ることで、給与所得控除も活用可能。
- 将来の退職金制度も設けることができ、税金対策になります。
- 経費の範囲が拡大し、法人名義の生命保険なども経費計上できます。
- 資金調達の手段が豊富
-
- 法人格を持つことで、個人事業と比較して、事業の継続性や透明性が担保されやすい場合があります。
- 投資家からの出資を受け入れることもできます。
- 株式会社であれば、株式の発行による出資の受け入れや、社債の発行などによる資金調達方法もあります。
- 優秀な人材確保がしやすい
- 「法人で働きたい」という求職者は確実に存在します。健康保険や厚生年金などの社会保険料を会社が負担することで、福利厚生制度も充実させやすいです。
困るところ(デメリット)
- 設立・維持にコストが発生
-
- 株式会社:設立時約 20 万円 + 年間維持費約 10 万円
- 合同会社:設立時約 6 万円 + 年間維持費約 7 万円
- 事務処理が複雑になる
- 法人税申告、社会保険の各種手続き、登記変更など、専門知識が必要な業務が増加します。税理士への依頼も実質必須となります。
- 赤字でも税金が発生
- 法人住民税(均等割)は、赤字でも年間約 7 万円の納税義務があります。
- 廃業時のコストも高い
- 事業を終了する際も、解散・清算登記など、個人事業主より手続きが複雑で費用もかかります。
【重要】法人成りのベストタイミング
税務(消費税・各種手続きの時期など)の観点
- 新設法人の消費税の取扱いは、資本金や届出の有無、インボイス登録の状況、第1期の長さなどで変わる場合があります。免税の可否や届出期限に影響することがあるため、想定する売上や事業計画と合わせて確認しておく考え方があります。
- 年末調整・個人の確定申告時期と作業が重なると、社内外の実務負荷が高まることがあります。手続きが集中しにくい月を選ぶのも一案です。
税理士の繁忙期の観点
- 一般に、2〜3月(個人確定申告)や3月決算の申告が重なる時期は依頼が集中しやすい傾向があります。サポート体制やスケジュールの取りやすさを重視するなら、これらの時期と決算・設立初年度の重要手続きが重ならない配置を検討する考え方があります。
自社の繁閑期・オペレーションの観点
- 繁忙期の直前・最中の期末は、棚卸や決算作業がタイトになりがちです。業務が落ち着く時期や在庫が少ない月を期末にすることで、実務面の負担を抑えやすくなることがあります。
- 決算後の納税は一定の期限内に発生します。資金繰り計画と照らし、支出が重なりにくい時期に納税が来るよう期末を設定する考え方もあります。
どの観点を優先するかは、事業モデルや成長計画、社内体制によって異なります。複数の候補月でカレンダーを作り、税務上の影響・実務の負荷・資金の動きを並べて比較したうえで、必要に応じて専門家に確認しながら決めていくアプローチが無難です。
具体的な⾦額は、法⼈の維持費⽤‧税理⼠への顧問料‧社会保険料負担等を総合的に考慮し、個別にシミュレーションして判断する必要があります。
FAQ|よくある質問
-
Q
法人成りすると必ず節税になる? -
A
必ずではありません。年間所得金額800万円程度が一つの目安と言われますが、家族構成や他の収入、経費の内容、社会保険料の負担などによって個人により大きく異なります。法人の維持費用や税理士への報酬も含めて、しっかりシミュレーションする必要があります。 -
Q
個人事業主から法人への移行は大変? -
A
手続き自体は1-2ヶ月程度ですが、取引先への通知、契約書の変更、許認可の移行など、事前準備がとても大切です。また、事業用口座の開設や印鑑の作成なども必要になります。 -
Q
法人成りしたら税理士は必要? -
A
法的義務ではありませんが、実際にはほぼ必須です。法人税申告書の作成がとても複雑なので、税理士への依頼費用を考慮しても法人成りのメリットの方が大きいかどうかが判断のポイントです。 -
Q
一人だけの法人でも意味がある? -
A
あります!福岡では、一人だけの株式会社・合同会社もよくあります。社会的信用が向上することと、節税効果が主なメリットです。ただし、固定の維持費用は発生します。 -
Q
合同会社と株式会社、どっちがいい? -
A
設立費用を抑えたい、家族や仲間だけでやりたいなら合同会社。将来の株式上場や大規模な資金調達を考えているなら株式会社です。合同会社は有限責任で、株式会社より手続きが簡単です。 -
Q
消費税との関係はどうなる? -
A
個人事業主で売上高1,000万円を超えると2年後から消費税の納税義務が発生します。法人成りすると新たに2年間の免税期間がもらえる可能性があります。このタイミングで法人成りを検討される方が多いです。 -
Q
家族経営の場合は何か特別な注意点がある? -
A
あります。家族への給与は個人事業主では経費になりませんが、法人では役員報酬や給与として経費計上できます。ただし、適正な金額設定が必要で、税務署の調査でチェックされやすい項目でもあります。 -
Q
社会保険料の負担はどう変わる? -
A
個人事業主は国民健康保険・国民年金ですが、法人成りすると健康保険・厚生年金への加入が義務になります。保険料は会社と個人で半分ずつ負担するため、実質的に負担が増加するケースが多いです。 -
Q
赤字が続いている場合でも法人成りした方がいい? -
A
一般的にはおすすめしません。法人は赤字でも法人住民税(年間約7万円)がかかります。また、赤字を翌年以降に繰り越せる期間は法人の方が長いですが、まずは黒字化を目指すことが先決です。 -
Q
副業から本業に移行するタイミングは? -
A
副業での年間所得が本業の給与を超えた、または安定して月50万円以上の収入が見込めるようになったタイミングが一般的です。ただし、本業を辞める前に十分な準備期間を設けることが重要です。 -
Q
銀行融資にはどんな影響がある? -
A
法人か個人かだけで有利・不利が決まることはありません。金融機関は返済原資(利益・キャッシュフロー)、事業計画の実現性、自己資本や資金繰り、税・社会保険の納付状況、担保や保証、取引実績などを総合的に審査します。設立直後の法人は決算実績が少ないため、個人事業主時代の実績や代表者の信用・資産が重視されることがあります。決算が整い黒字が続く場合は、事業形態にかかわらず評価材料になりやすい、という整理が適切です。 -
Q
許認可が必要な業種の注意点は? -
A
建設業、美容業、飲食業など許認可が必要な業種では、法人成りの際に許認可の移行手続きが必要です。業種によっては時間がかかるため、事前に確認して計画的に進めることが大切です。 -
Q
法人成りして後悔することはある? -
A
あります。事務処理の煩雑さ、固定費の発生、税理士費用の負担などで「個人事業主の方が良かった」と感じる方もいます。特に売上が下がった時に固定費の重さを実感することが多いです。 -
Q
年収と所得の違いがよくわからない -
A
年収は売上のこと、所得は売上から経費を引いた利益のことです。法人成りの判断は「所得」で行います。たとえば年収1,500万円でも経費が700万円なら所得は800万円となり、これが判断基準になります。 -
Q
資本金はいくらに設定すればいい? -
A
最低1円から設定可能ですが、社会的信用を考えると100万円以上がおすすめです。ただし、1,000万円以上にすると消費税の免税期間がなくなるため注意が必要です。業種や取引先との関係も考慮して決定しましょう。
【福岡ならでは】地域の特色を活かそう
福岡で事業を行う時の特徴
- 創業支援制度が充実
- 福岡市などの自治体や商工会議所の創業支援メニューを活用できることが多く、手続きや補助金の情報を得やすいといった傾向があります。
- IT・クリエイティブ系への支援
- イベントやコミュニティ、特定分野向けの補助金が整っているケースがあり、対外的な信頼を確保したい場面では法人格が機能しやすいことがあります。
- 地域の金融機関との関係性
-
福岡では、同一都道府県内に大規模な地方銀行が2行並ぶ構図が見られます。
このような状況は全国的にも比較的まれとされ、事業者にとって相談先の選択肢が広い地域と言えます。
なお、融資の審査は事業計画や返済可能性などの総合評価で行われ、会社形態だけで有利・不利が決まるものではありません。
業種別アドバイス
- 飲食業
- 立地が最重要。個人事業主でも対応可能ですが、従業員を多数雇う段階では法人化を検討する考え方があります。
- IT・コンサルティング
- 対外的な信頼や契約要件の観点から、法人格で進めるとスムーズな局面がみられます。
- 建設・製造業
- 許認可や公共工事の入札を視野に入れる場合、資本金や体制整備を含めた法人化の検討が現実的です。
- 小売・サービス業
- 売上規模と従業員数で判断。年商の伸びや雇用計画に合わせて、段階的に法人化する選択肢があります。
まとめ
個人事業主と法人、どちらの事業形態にもそれぞれ良いところがあります。大切なのは、「今のあなたの状況」と「 3-5 年後の事業計画」をハッキリさせて判断することです。
個人事業主がおすすめの人:
- 年間所得金額がまだそれほど多くない段階
- 一人で自由に事業を継続したい
- 開業手続きを簡単に済ませたい
- 初期費用をできるだけ抑えたい
- フリーランスとして専門性を活かしたい
法人成りがおすすめの人:
- 年間所得が一定水準を超えている ※
- 従業員を雇用する予定がある
- 大企業との取引を拡大したい
- 将来的な事業拡大・資金調達を目指している
- 社会保険や退職金制度を整備したい
※具体的な金額は個人の状況により異なるため、税理士などの専門家への相談をおすすめします。
迷った時は、「とりあえず法人成り」ではなく、まずは個人事業主でスタートして、上に書いた条件に当てはまってきたタイミングで法人成りを検討するのが安全で一般的な方法です。福岡での起業・法人設立は、地域の特性や創業支援制度を活用することで、より有利に進められます。自分の事業にとって最適な選択ができるよう、分からないことがあれば中小企業診断士や税理士といった専門家に相談しましょう。法人成りは単なる税金対策ではなく、事業の成長段階に合わせた重要な経営判断です。しっかりと情報収集して、ベストなタイミングで決断しましょう。
関連記事