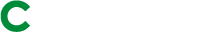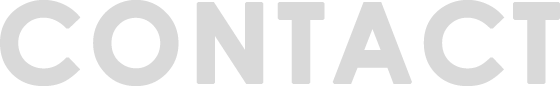福岡で独立開業を考えているあなたへ。「自分の力でお店や事業を始めたい!」その一歩を、失敗しにくい手順で案内します。開業手続きの基本から、福岡ならではの支援拠点・制度、失敗しがちなポイントまでを中小企業診断士がやさしく解説します。
- ✔ 個人事業主とは:会社を作らず個人名義(屋号可)で継続的に事業を営む人。開業届で今日からスタート可
- ✔ 必須手続き:開業届/青色申告承認申請/国民健康保険・国民年金の切替
- ✔ 福岡の強み:創業の相談拠点と制度が充実。金融機関の選択肢も豊富
- ✔ 成功のカギ:準備の徹底・屋号と会計基盤づくり・最新情報の確認
個人事業主って何?基本と判断ポイント
1-1. 個人事業主とは
会社を作らずに個人の名義で継続的に事業を営む人を指します。「武蔵ベーカリー」「太陽デザイン事務所」のように、あなた自身の名前や屋号で活動します。
会社員との根本の違い:個人事業主には「自分への給料」という概念がありません。事業の儲け=あなたの所得であり、同一人物内でお金を移しても経費にはなりません。
法律上、事業主本人や家族の労働の対価は必要経費にできないと定められているためです。
① 家計簿で考える
家計簿に以下のように書いたらおかしいですよね?
収入:お母さんから 10,000円 支出:自分へのお小遣い 10,000円
自分で自分にお小遣いをあげても、お金は増えも減りもしません。個人事業主の「自分への給料」も同じ発想です。
② 一人二役のたとえ
個人事業主は一人で「社長」と「従業員」の両方を演じているようなもの。
- 社長の自分:「従業員の君に給料を払うよ」
- 従業員の自分:「ありがとうございます」
でも実際は同じ人なので、お金は移動していません。
法人(会社)の場合は法律上「会社」と「あなた」は別人格です。
- 会社:「社長個人のあなたに役員報酬を払います」
- あなた:「ありがとうございます」
この場合は実際にお金が移動するので、会社の経費になります。
③ 税金の観点
もし自分への給料が経費として認められたら:
- 売上100万円 − 給料100万円 = 所得0円
- 税金も0円になってしまいます
- これでは税制度が成り立たないため、法律で不可とされています
④ では収入はどう扱う?
お祭りで綿あめ屋さんをやった場合で考えてみましょう。
・1日の売上:10,000円(綿あめ100個×100円)
・経費:3,000円(砂糖代・ガス代・場所代など)
・あなたの取り分:7,000円
この7,000円は給料ではなく、「事業で稼いだお金(所得)」です。給料のように「毎月決まった金額」ではなく、「頑張った分だけもらえるお金」なのです。
根拠:所得税法第37条第1項/所得税基本通達37-1
1-2. 個人事業主 vs 会社設立 かんたん判断
【分岐チャート】 A. 年間売上予想が 1,000万円を超えそう? → [YES] 会社設立を検討 / [NO] Bへ B. 年間の儲け(所得)が 800万円超の予定? → [YES] 会社設立を検討 / [NO] Cへ C. 従業員を雇う予定がある? → [YES] 会社設立を検討 / [NO] Dへ D. 取引先の多くが大企業(与信・取引形態で法人格を求められやすい)? → [YES] 会社設立を検討 / [NO] 個人事業主でスタート
迷ったらまず個人事業主で始め、必要に応じて法人化へ移行するのが一般的です。法人との違いは、個人事業主と法人化の違い・メリデメに詳しくまとめています。
1-3. 個人事業主のメリット・デメリット
メリット
- 手続きが簡単で費用も少なめ
- 意思決定の自由度が高い
- 書類作りの負担が比較的軽い
デメリット
- 信用面で法人に劣る場面がある
- 所得が増えると税負担が重くなりやすい
- 資金調達で不利な場合がある
- 事業上の債務は原則として個人が無限責任
開業前の準備:失敗しない5ステップ
家づくりと同じで、基礎を固めるほど後がラクです。
事業計画の具体化
やること
- 事業内容と価値提案を明確にする
- ターゲット顧客と提供チャネルを決める
- 競合と差別化の整理
- 収支のシミュレーション
福岡での相談先の例
- 福岡市 中小企業サポートセンターなどの地方自治体(融資制度・相談)
- Startup Cafe/Fukuoka Growth Next(創業相談・交流)
- 福岡商工会議所などの商工会議所や商工会の創業塾・専門相談窓口
資金準備
必要資金の目安
- 初期投資:業種次第で変動
- 運転資金:生活費+事業費の最低6か月分
- 緊急予備費:突発支出への備え
調達の選択肢
- 日本政策金融公庫(創業向け融資)
- 地銀・信金などの金融機関
- 福岡市・福岡県の制度融資(創業支援資金・新規創業資金 等)
- 各種補助金・助成金(募集時期や要件に留意)
屋号の決定
良い屋号かどうか
- 覚えやすく発音しやすいかどうか
- 事業内容が伝わりやすいかどうか
- 商標や既存名称と紛らわしくないかどうか
- ドメインを確保できるかどうか
注意点
- 「会社」「法人」などの語は使用不可
- 近隣での重複・混同を避ける
許認可の確認
主な例
- 飲食:食品営業許可(保健所)
- 美容:美容所開設届(保健所)
- 建設:建設業許可(県・市)
- 古物:古物商許可(警察)
- 旅行:旅行業登録(運輸局)
開業場所の準備
自宅開業
- 賃貸契約で事業利用の可否を確認
- 騒音・配送など近隣配慮
- 仕事環境の整備
事務所・店舗
- 立地と動線を十分に検討
- 初期費用と原状回復費を把握
- 契約条件と解約条項を確認
必要な手続きと書類:やることリスト
3-1. 税務署への提出書類
① 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)【必須】
- 期限:開業日から原則1か月以内(期限超過の罰則はなし)
- 提出先:所在地を所管する税務署
- 費用:無料
- 提出方法:窓口/郵送/e-Tax
書き方のコツ(3点)
- 事業内容は何を・誰に・どう提供するかを分かりやすく記載
- 屋号は未定なら空欄でOK
- 開業日は実際に開始した日で問題なし
持参するもの(例)
- マイナンバーカード等の本人確認書類
- 控え用(受付印をもらう)
② 所得税の青色申告承認申請書【節税メリット大】
- 期限:1/1〜15開業→当年3/15まで/1/16以降開業→開業から2か月以内
- 特典:最大65万円控除(要件あり)/55万円/10万円の3区分、赤字繰越 など
③ 従業員を雇う・給与を払う場合
- 給与支払事務所等の開設届:支払開始から1か月以内
- 源泉所得税の納期の特例:従業員10人未満なら年2回納付を選択可
3-2. 社会保険まわり
国民健康保険【必須】
- 手続先:住所地の市区町村
- 期限:会社退職の翌日から14日以内
- 他の選択肢:任意継続(退職日の翌日から20日以内)/配偶者の扶養
- 持参物例:本人確認書類、健康保険の資格喪失確認書類 など
国民年金【必須】
- 手続先:住所地の市区町村
- 期限:会社退職の翌日から14日以内
- 将来への備え:国民年金基金/小規模企業共済/iDeCo など
- 持参物例:本人確認書類、年金手帳(基礎年金番号がわかるもの) など
3-3. 福岡県内の主要税務署(管轄の目安)
- 福岡税務署:中央区・南区
- 博多税務署:博多区・東区の一部
- 香椎税務署:東区の一部・糟屋郡(新宮町・久山町・粕屋町・篠栗町・須恵町・宇美町・志免町)ほか
- 西福岡税務署:西区・城南区・早良区・糸島市
管轄区域は変更されることがあります。提出前に国税庁サイトで最新情報をご確認ください。
所轄税務署の調べ方:国税庁「税務署所在地検索」に住所を入力すると担当税務署が表示されます。
福岡で個人事業主になるメリットと地域の特徴
4-1. 福岡の創業支援(制度・拠点)
具体的な金利や上限額は年度で変わるため、ここでは制度名と拠点にとどめます。
- 制度融資:福岡市の商工金融資金(例:創業支援資金 など)/福岡県の中小企業融資制度(例:新規創業資金・成長支援資金 など)
- 相談・交流拠点:Startup Cafe、Fukuoka Growth Next、商工会議所の創業窓口
詳細条件(上限額・金利・保証料・対象要件)は年度改定があります。必ず最新の公式案内で確認してください。
最初の一歩: 予約は各拠点の公式サイトまたは電話で。持ち物は本人確認書類・簡単な事業アイデアメモ・概算の収支見込み。窓口により初回無料または一部有料のことがあるため、事前に確認しましょう。
4-2. 産業特性を活かした開業例
IT・ゲーム・Web関連
- 都心部(天神・博多)に企業・人材が集積
- 創業支援拠点やコミュニティが豊富
観光・サービス
- 国内外の来訪者が多く潜在需要が大きい
- 食・体験・ホスピタリティ分野で差別化の余地
4-3. 金融機関との付き合い方
福岡銀行や西日本シティ銀行など地元の主要地方銀行や信金、日本政策金融公庫など、複数の金融機関に相談の間口を持つことが大切です。制度融資の取次や創業相談、口座開設、キャッシュレス導入など、各行のメニューを比較し、自社の計画に合う選択肢を選びましょう。
開業後にやること:実務ガイド
5-1. 事業用の銀行口座
事業と私生活の資金は必ず分ける。屋号付き口座の開設は管理の要です。
5-2. 会計ソフトの導入
選ぶ際の主なポイント
- 操作が直感的かどうか(毎日の入力が続けやすいか)
- サポートが手厚いかどうか(ヘルプ・チャット等)
- 料金が適正かどうか(機能と費用のバランス)
- 税理士と連携しやすいかどうか(共有・権限設定)
- 口座・カード連携が安定しているかどうか(自動取得の精度)
- e-Tax/電子帳簿保存に対応しているかどうか
主なクラウド会計 ※順不同・機能例であり推奨順ではありません。
- freee会計:タグ(取引先・部門・メモタグ・セグメント)を使って横断集計が可能。タグ設計を工夫すれば、プロジェクト別損益など簡易的な管理会計にも応用できます(プラン要件あり)。
- マネーフォワード クラウド会計:銀行・カード連携や周辺クラウド群との統合が強み。
- 弥生会計 オンライン:長年の利用者が多く、申告書作成の学習素材が豊富。
クラウド会計の主なメリット(例):明細の自動連携/データの自動バックアップ/法令・様式のアップデート対応。
5-3. 営業・宣伝の準備
① Web・SNS
掲載したい情報(例)
- 提供サービスの内容(何を、誰に、どう価値提供するか)
- 連絡先(電話・メール・問い合わせフォーム)
- 運営者のプロフィール(信頼の根拠)
- お客様の声(第三者評価)
② 名刺・チラシ
- 清潔感があるかどうか
- 文字が読みやすいかどうか
- 情報の優先順位が整理されているかどうか
③ 人とのつながり
- 商工会議所・商工会の交流会(ローカル情報を得やすい)
- 異業種交流会(顧客紹介や協業のきっかけ)
- 業界コミュニティ(最新動向や事例共有)
5-4. 保険の検討
必須
- 国民健康保険/国民年金(加入・納付は確実に)
検討したい保険
- 小規模企業共済:退職金的な備え。掛金は全額所得控除
- 損害保険:設備・商品を守る
- 賠償責任保険:対人・対物のリスクに備える
- 所得補償保険:病気・けが時の収入減をカバー
- 事業用自動車保険:営業で車を使う場合
病気やケガで長期休業すると、個人事業主は売上が止まり収入がゼロになる可能性があります。
所得補償保険や小規模企業共済などで、万一の生活費・固定費をカバーする設計を検討しましょう。
従業員を雇う場合:雇用保険・労災保険の加入手続きを忘れずに。
業種別のポイント
6-1. 飲食業
- 食品営業許可/食品衛生責任者の配置
- (一般的に)特定用途で収容人員30人以上の場合は防火管理者の選任が必要。所轄消防署で要件を確認
- 立地・コンセプト・原価管理・衛生管理がカギ
6-2. 美容室
- 美容所開設届/美容師免許確認/設備基準の充足
- 内装・設備費の比重が大きいため、費用は規模差が大。見積もりで把握を
6-3. IT・Web関連
- 初期投資を抑えやすく、自宅開業もしやすい
- 著作権・セキュリティ・継続学習への備え
6-4. コンサルティング
- 許認可は原則不要(業種により例外あり)
- 専門分野の明確化と実績の可視化が重要
6-5. 建設業
- 500万円以上の工事は原則として建設業許可が必要
- 市内再開発など地域需要に機会
よくある失敗と回避策
7-1. 資金まわり
- 売上見込みが楽観的すぎる → 7割見積で安全側に
- 運転資金不足 → 生活費6か月分を確保
- 設備投資過多 → 段階導入で固定費を抑制
7-2. 税務・経理
- 領収書の紛失 → 保存は7年間。クラウド保管も活用
- 申告遅延 → 早めに会計ソフト導入&月次締め
- 消費税の見落とし → 売上や取引先に応じインボイス登録を検討
7-3. 集客・宣伝
- 「作れば売れる」の思い込み → 顧客像の明確化と検証
- 差別化不足 → 強み(USP)を一言で言える形に
- 顧客の声を活かさない → 小さく改善を回す
7-4. 健康管理
- 過労・睡眠不足 → 休息を計画に組み込む
- 病気時の収入減 → 所得補償保険の検討
- 長期休業時の収入ゼロに備える → 生活費6か月分の準備+保険で固定費をカバー
お金と税金の基礎
8-1. 帳簿付け
- 青色申告(10万/55万/65万円控除)に合わせて記録レベルを選ぶ
- 複式簿記+e-Tax/電子帳簿保存で最大65万円控除
8-2. 経費の考え方
- 事業との関連が説明できる支出が対象
- 自宅兼事務所は按分(面積・時間など根拠をメモ)
- レシート・請求書は7年保存
8-3. 消費税の基礎
- 基準期間(2年前)の売上1,000万円超で課税事業者
- 特定期間(前年上半期)1,000万円超でも課税対象
- インボイス制度:登録の有無で取引影響が変わる
FAQ|よくある質問
-
Q
開業届を出さなくても事業はできる? -
A
法的には可能ですが、青色申告の適用、屋号口座の開設、融資審査などで開業届の控えが求められます。提出を強くおすすめします。 -
Q
個人事業主でも屋号で銀行口座は作れる? -
A
作れます。開業届の控えが必要なことが多く、銀行により条件・審査が異なります。 -
Q
家族を従業員にする際の注意点は? -
A
青色は青色事業専従者給与の届出が必要。白色は専従者控除を確認。金額は相場に照らして妥当性を。 -
Q
副業からいつ「事業」になる? -
A
営利性・継続性・反復性があり、規模や実態が社会通念上「事業」と認められるとき。判断が難しければ税務署や専門家に相談を。 -
Q
お店を始めたらすぐ確定申告が必要? -
A
儲け(所得)があなたの基礎控除額を超えると申告が必要です。最新の控除額・要件は国税庁の案内で必ず確認してください。 -
Q
事業用クレジットカードは必要? -
A
必須ではありませんが、経費の一元管理や会計ソフト連携で記帳が効率化します。与信や年会費、ポイント設計が事業規模に合うか確認しましょう。 -
Q
福岡市外から福岡に引っ越して開業する場合の注意点は? -
A
住民票の移転・所轄税務署の確認・地域の商習慣の把握がポイント。制度融資や創業相談は自治体で異なるため、市区町村・県・商工会議所の最新案内を事前に確認しましょう。 -
Q
お店を始める時期はいつが良い? -
A
税務上は年初開業だと1年の収支把握が容易。事業面では繁忙期を避けてトライアル期を確保できる時期、資金面では運転資金を十分に積めた時が目安です。ライフイベントとの調整も忘れずに。 -
Q
失敗した場合はどうすれば良い? -
A
早めに損益の見直しと資金繰り対策を実施。撤退時は廃業届・青色取りやめ・給与支払事務所の廃止届など必要手続きを行い、最終の確定申告を忘れずに。 -
Q
税理士はいつから相談すべき? -
A
開業前の計画段階、帳簿が煩雑になった時、青色65万円控除の要件を満たしたい時、消費税の課税事業者になった時が目安。費用対効果と相性で選びましょう。
関連記事
まとめ
- 基礎を固める:計画・資金・許認可を事前に確認
- 会計と税務を整える:クラウド会計を導入し、月次で整える
- 福岡の強みを活かす:制度融資・支援拠点・ネットワークを使いこなす